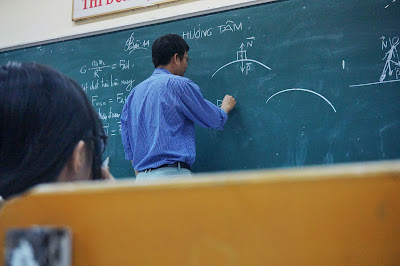コロナ、マスクしたままカット: 14か月ぶりに美容院に行きました I went to the hair salon for the first time in 14months

1年2か月の間、美容院に行かなかった私 去年の9月が最後の美容院行でした。 それから14か月強、行ってなかったのです。 理由は、2019年の秋から2020年の新年まで、猛烈に忙しくて行く暇がなかったこと。 そして、2020年2月に入って、行こうと思ったら、コロナが広がってきて躊躇してしまったこと。 この二つが原因です。 2020年7月に 今が人生でいちばん長い髪 という記事を書いています。 美容師さんによると、髪は1か月でだいたい1cmから1cm強伸びるそうです。 ということは、 1cm x 14= 14cm 14cm以上、伸びたんですね。 たしかに、会う人ごとに、 髪、伸びましたね~ と言われていました。 途中、自分で切ってみた 今回切ってもらった美容師さん曰く、 じゃあ、前はショートだったんですね? たしかにちょっと短い部分がありますけど, これはショート時代の名残でしょうかね。 と言うので、 前がショートだったのはその通りなんですが、 ちょっと短い部分があるのは、 自分で切ったからじゃないかな? と返事すると、 ヒエー。自分で切ったんですかあ。 と驚いていました。 そういえば、ちょっと右と左で長さが違いますね。 そうなの。後ろはむずかしいね。 youtubeなんかで、セルフカットのレクチャーみたいなのがありますよねー と、セルフカットの話題で話が弾みました。 美容師さんにとっては営業に差し支える話題でしょうが、ノリノリで話していました。 まあ、セルフカットの一般的限界をご存じでしょうからね。 結局5cm切ってもらった。すごい毛の量がフロアに落ちていました もともと、なんの変哲もない 横分けまっすぐの前髪なしですから 全体をくるっと5㎝切ってもらって、後ろだけ少し軽くしてもらって終了です。 毛が多い性質なので、床にはかなりの量の毛が落ちていました。 1年ほど前から、髪を染めるのをやめたので(自分でするカラーもやめた)、その歴史が刻まれた髪の束は、 茶色(結構オレンジがかっていました)、黒、白髪の三色に彩られて床に小さな山をなしていました。 非常に空いていたので、コロナの心配はしなかった わりに広いサロンでしたが、お客さんは私を含めて二人しかおらず、その一人も途中で帰ったので、私ひとり。 私も、美容師さんもマスクをしています...